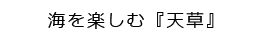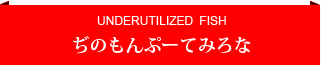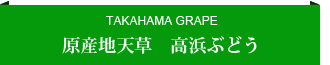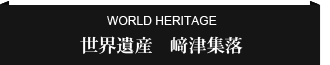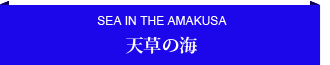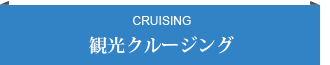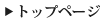南蛮文化がもたらしたもの

南蛮文化はいままで日本になかった多くのものを与えてくれました。キリスト教(南蛮文化)とかかわりの深い天草ではコレジヨと呼ばれる学び舎が設けられました。ここは一般教養、高等教育などを学ぶ場として、多くの人が学問、芸術を学び教科書はポルトガル語やオランダ語で書かれたものを使っていました。宣教師がポルトガルから来ていたこともあり、彼らの事をバテレン、使っている言葉をバテレン語と呼んでいました。バテレンは、ポルトガル語で神父を意味するの「Padre」が語源です。
また貿易も盛んに行われており、幕府や役人にとってはこちらの方が重要視されていました。貿易品には日本にはなかった品が多く、硝石や生糸、絹織物は大名や国人の趣向品として好まれました。火薬の原料にもなる硝石などは戦争の道具として重宝されました。貿易とは少しはずれますが、当時の流行なのか刀のつばに十字架を模した装飾など、幅広いところで南蛮文化を見ることができました。
農民をはじめとする多くの住民は南蛮文化そのものよりもキリスト教など心のよりどころを得たことが最も大きいものでした。戦国時代当時の人々にとって死が身近にあったこともあり、皆が平等に救われると諭したキリスト教の教えに多くの人が賛同することになります。キリスト教の教えは人々の救いとなるのですが、逆にこのことが後に信者たちを追いつめ、苦しめることになります。
 |  |
 |  |