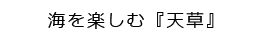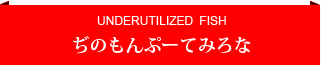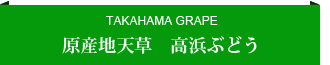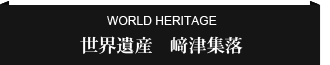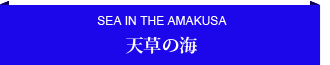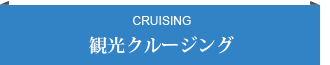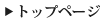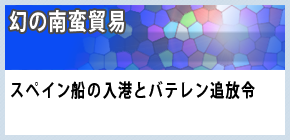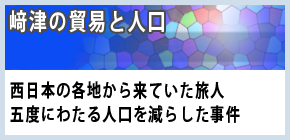石高から見る﨑津の動向
徳川吉宗が納める享保の時代の話です。
﨑津の石高が28石しかありませんでした。天草全体で2万石あった頃に28石という数字は、天草内で最低の数字です。石高とは1石1人として、1人を一年間養える生産量(主な生産品は米)をあらわした単位です。崎津内の石高で住民をまかなうと28人しか維持できない計算になります。当然ながら﨑津の住人分の石高が足りませんので﨑津外から輸入することで補うことになります。
﨑津は漁村です。天草全体の四分の一を占める漁獲量を誇っていた﨑津は他にはない海産資源がありました。これらの資源を持っていたこともあり、﨑津は輸出数、輸入数で天草トップを誇っている貿易の町でした。また、貿易また商人などの滞在日数が他の地域と比べ長い事が﨑津の特徴で「もてなしの町」として栄えていた事がうかがえます。また天草ブランドとして「干鰯(ほしか)」が有名でした。干鰯はイワシなどの小魚の乾物で作られた堆肥です。天草干鰯は遠方の地域からも需要があるほど重宝されていました。
人口の増減
﨑津は1800年初頭から1300人ほど住人がいたとされていました。
他の地区が500人程度でしたので非常に多くの人口を抱えていた﨑津ですが、1800年初頭からの事件でこの人口が大きく変動する事となります。
最初は1801年、天然痘が流行します。天然痘自体は﨑津に限らず日本中で流行していました。天然痘は、はしかのように一度発症すると二度目の発症はない病ですが、感染力の強さや乳幼児・抵抗力の低い人の死亡率の高さから当時非常に恐れられた疫病です。
天然痘の流行から12年後、天然痘が再流行します。
人口が右肩下がりになる中、1823年に熱病が流行します。熱病に関しては特定の病名があげられていませんので詳しくはわかりませんが、この熱病が住民を苦しめる中、大きな火災が起きます。病に苦しむ中の火災ということで被害が広がり民家の約半数が火災の被害を受けたとされています。
そののち天然痘の再々流行、漁船と思われる大型船の事故と数々の事件を経て﨑津の人口は最盛期の半分にまで減ってしまいます。当時日本全体で人口の増加している中、﨑津は人口の激減をした地域でした。人口が増え始めるのはこれから少し先の明治に入ってからになります。